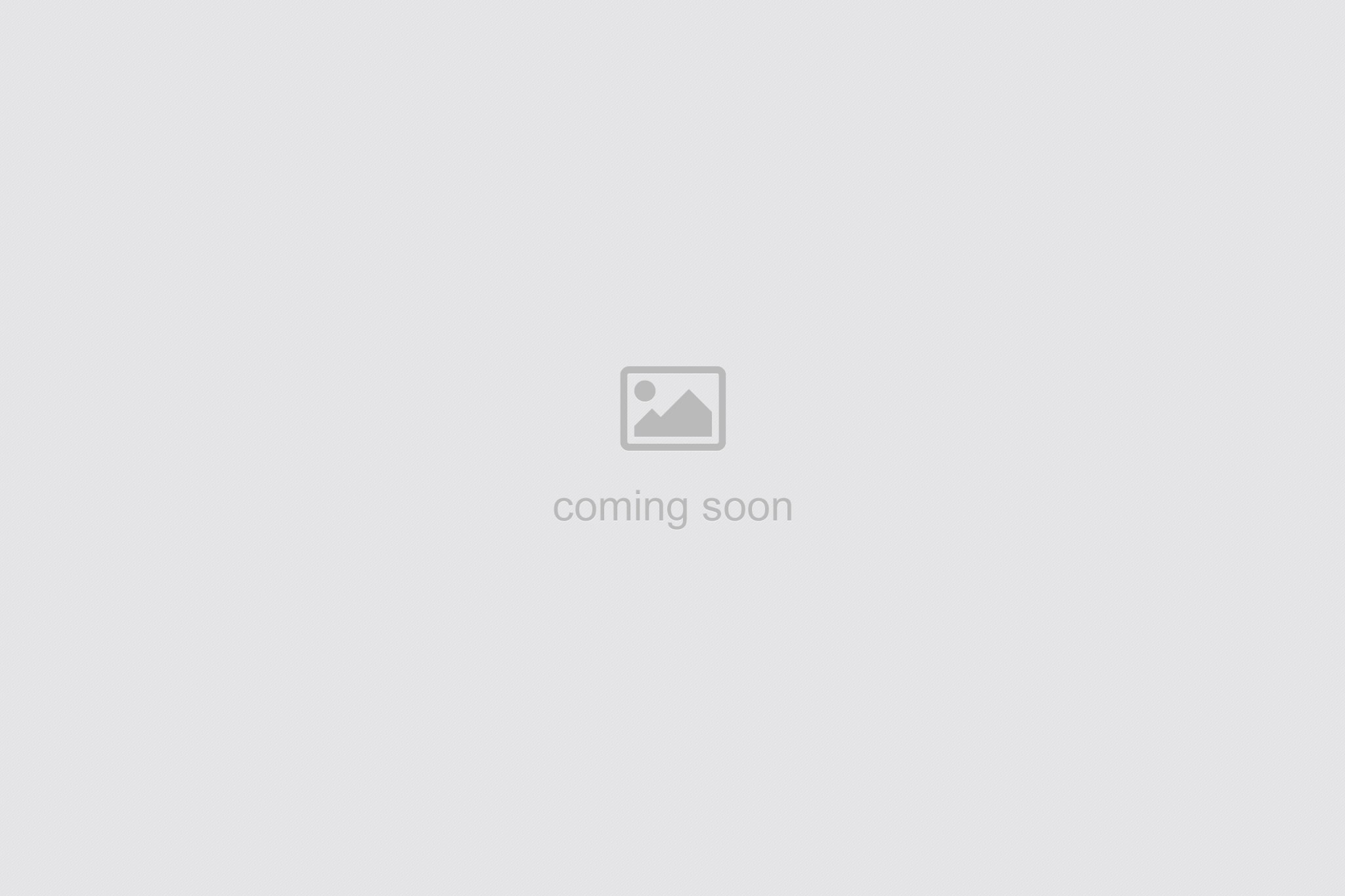理事長ブログ
理事長ブログ
2019年12月24日、身延山(1,153m)登山300回達成!
2019-12-23
分解ということ
2019-10-10
最近「分解の哲学」という書物に出会った。地球上のすべての存在は、最終的に分解して消滅するというものだ。人間も例外ではない。中に屑拾いの話が出てくる。屑(くず)とは、もちろん不要になった、役に立たなくなった物の総称である。「人間の屑」とは役立たずの蔑称である。江戸時代にあっては、屑屋はほとんど資本のいらない、誰もが気軽に出来る職業であったという。屑と言えば紙くずを連想する。不要になった紙くずを集めて再生することで経済のルールにのっとている。屑を拾う人がいなければ、屑がちまたに溢れ、たちどころに生活に支障を来す。今の日本では、自治体によるゴミの収集が当たり前になっているが、いずれはこの当たり前のサービスがなくなることだって考えられる。誰かが嫌な役目を担ってくれるから生活が成り立っていると、立ち止まって考えることが必要ではないか。プラスチックの容器が世界的に問題になっている。つまり、すべての物が分解して消滅するという哲学の範疇から外れる物は地球の存続にとって有害である。プラスチックの廃棄が増え続けば地球上はプラスチックで溢れる。自治体も収集はするが詰まるところ再利用の策はなく、焼却という形で消滅させている。CO2の排出量が問題視され、いずれは焼却も出来なくなる。石油由来の製品を使用しないという大きな決断が迫られている。人は一度安易な物に慣れ親しんでしまうとなかなかそこから抜け出すことは出来ない。「分解の哲学」は示唆に富んだ書物である。是非読んでみることをお勧めする。
北岳登山(日の出と富士山)
2019-08-10
事前の情報では二俣を回った方が楽ですよなんて聞いていたものの、いざ二俣から頂上を目指そうとすると谷沿いに直線の急勾配。足下はガレの多い不安定な道。おまけに晴天で木陰もなく直射日光が容赦なく照りつける。しばらくすると林が現れたのでホットするも、目指す肩の小屋は遥か遠く。肩の小屋まで30分との標識にホッとして目を彼方に向けると稜線の遙か彼方に人の姿が。果たして30分であそこまで行けるのか。その先はどうなっているのか、疲れた身体に鞭打って1歩また1歩と牛の如き歩を進める。言うまでもなく山に登るということは頼りになるのは自分のこの身体のみである。泣こうが叫ぼうがどうにもならない。意思に鞭打ち歩を進めるしかない。ただ、言えることは1歩進めば目的地に1歩近づく。今登っている誰もが同じ苦しみを味わっているんだ。自分だけではない!そんな思いを抱きながらひたすら歩いて行くと彼方にテントが見え始める。ここまで来てやっと今日の目的地肩の小屋が現実になる。7時間20分よく歩いたものだ。自分を褒めてやる。ここまで来れば頂上を極めることが現実味を帯びる。頂上はすぐそこに見える。今夜休息をとって明朝頂上を極めるんだ!
北岳登山(通称肩の小屋のある北岳の肩)2019.8.10
2019-08-10
8月4日午前7時50分発広河原行のバスに間に合うように家を出発して、午前7時過ぎに芦安の市営駐車場に到着。朝一番のバスは5時15分ということで駐車場は満車状態。バスの発着所から大分離れた第8駐車場に駐車して、重いリュックを背負って歩くこと15分。バスは山道をひたすら走ること1時間20分(予定所要時間は1時間)。インフォーメーションセンターで登山届を出していよいよ出発。吊り橋を渡って登山口へ。9時20分登山口を歩き始め木立の中をひたすら歩む(よじ登る)こと2時間30分、正午ごろ御池小屋に到着。雲ひとつない快晴だが木立の中を進む登山道は涼しくここまでは心地よい登山でした。御池小屋でソフトクリーム(600円)を食べて30分ほど休憩。比較的景色が良いですよとのインフォーメーションセンターの職員の助言を得てコースに二俣を選んだ。二俣まではどちらかというと下るような道を歩くこと40分、雪渓が目の前に現れた。
ご朱印集め続編
2019-06-21
ご朱印集めはおそらく江戸時代に始まったと思います。神社仏閣が参拝者を増やそうとご朱印帖なるものを作って・・・いや最初は参拝者が参拝の記念に何か書いていただけませんか、などとお願いして始まったのかもしれません。参拝する側も一枚ずつ取っておくと散逸してしまうので、半紙を綴じて持参する人も現れ始めます。そんな要望が増えてくると、いっそご朱印帖を作ろうなんて考える神社仏閣が出てきて今回のブームに結びついたと思います。さて、究極のご朱印集めは、掛け軸です。これはもう本格的です。私も最初見た時は息をのみました。すげーって感じです。仏間もしくは床の間に飾ってご本尊として朝夕に拝むんだと思います。この軸に書くのも覚悟がいります。他の神社仏閣の朱印と比べて見劣りがするような文字では恥になります。こんな時、僧侶は字が上手なことは当たり前なことだと思い知らされます。自分の書いた朱印の文字が立派なお宅の仏間に掛けられ信仰の対象になるんだと思うと、もっともっと練習をしておけば良かったと反省します。
では、神社仏閣を参拝して集めたご朱印帖はその後どのような運命をたどるんでしょうか。老後の思い出話の資料になることもあるでしょう。御朱印帖を開いて参拝した時の光景を思い出す手がかりになりますよね。でも、個人のアルバムと同様、その人が亡くなれば無用の長物となります。そうならないためのとっておきの方法をお教えしましょう。
高齢者が激増し、終活の文字を目にし、耳にすることも珍しくなくなりました。60歳を節目に終活を真剣に考えましょう。ご朱印帖は行衣(ぎょうい)、お珠数(じゅず)と一緒にお仏壇の引き出しにしまっておく。自分が死んだら、行衣を着せて(「死に装束」)、左手に珠数を持たせて棺桶に納めて下さいと家族に話しておきます。ご朱印帖はお棺入れてもらいます。生前にお参りをした神社仏閣のご本尊があなたをお迎えに来て無事お釈迦さまのもとにお連れして下さいます。そのためのご朱印帖なんです。
さあ、今日からは心新たにせっせとご朱印帖を持って神社仏閣にお参りしましょう。私はもう7冊目ですよ!